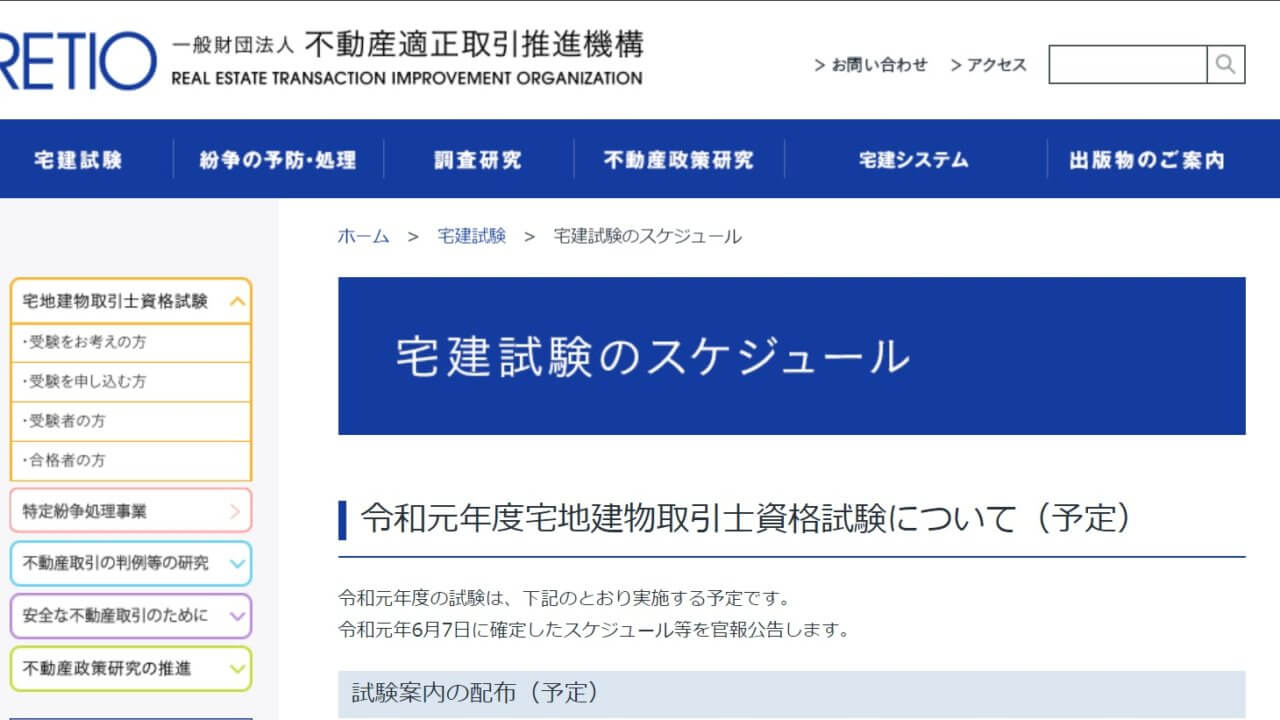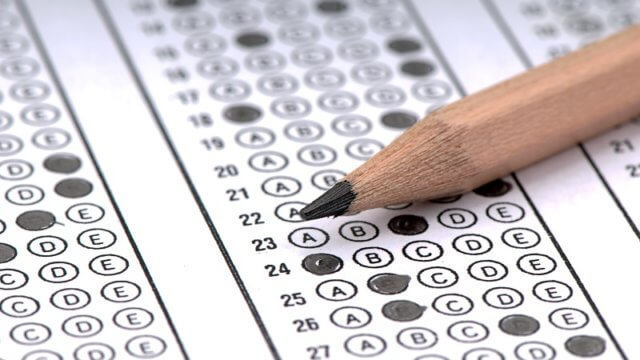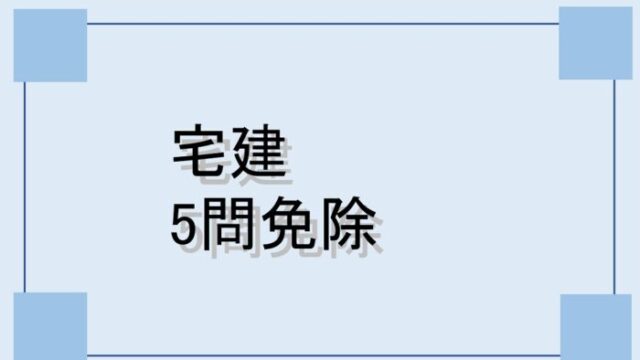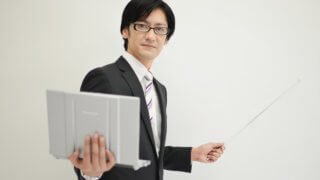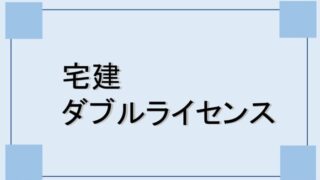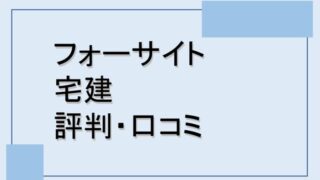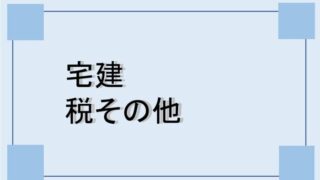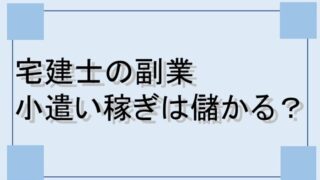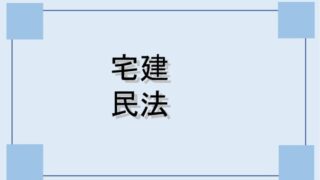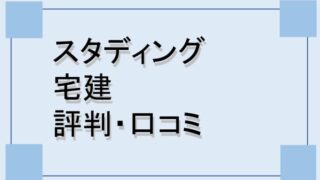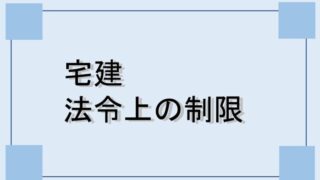こんにちは、トシゾーです。
この記事では、2021年(令和3年)宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の試験日、試験スケジュール、受験手続等をまとめました。
早速ですが、2021年(令和3年)の宅建試験日は
令和3年10月17日(日)13時~15時(2時間)
です。
このように、本来、宅建試験は年1回の実施となります。
しかし、本年は10月の他に、12月にも試験が実施されることになりそうなのです。
その理由は、感染拡大の影響により、一部の試験地(都道府県)において、10月だけでは試験会場が不足することが予想されているからです。
とは言え、全国すべてで12月試験が実施されるわけではありません。試験地ごとに、受験申込者数が10月の試験会場の受験可能人員を上回った場合には、10月と12月に分けて試験を実施するとのこと。
※令和2年度も、感染拡大の影響により10月に例年どおり試験会場を借り上げることが困難となり、11の都府県において、受験者を10月と12月に分けて試験が実施されました。
その際、10月と12月のどちらの試験日での受験であるかは試験機関によって指定されます。受験申込者が選ぶことはできないのです。
また、12月受験に振り替えられた場合でも、試験日・試験会場を変更したり、申し込みの取消はできません。
つまり・・・・
- まずは10月に試験を受けるつもりで申し込む
- 自分の地域で、受験申込者が会場収容人員を上回った場合、強制的に12月試験に変更される可能性がある
- 12月試験になったとしても、申込取消はできない
ということです。
・・・ちょっと受験者に優しくないルールだなぁ、という気もしますが、宅建は毎年20万人以上も受ける大規模な試験ですし、そもそも感染症流行の動向も予想できませんので、仕方がない部分もありますね。
嘆いていても仕方ありませんので、
- しっかり受験手続やスケジュールを頭に入れ、10月と12月、どちらの受験になっても合格できるように対応する
ということが最も重要かと思います。
ぜひ、この記事を読んで、宅建試験日やスケジュール・受験手続を把握し、適切な行動をしてくださいね。
なお、宅建試験の出題内容や出題科目の詳細ついては、下記の記事にまとめてありますので、そちらも参考にしてください。
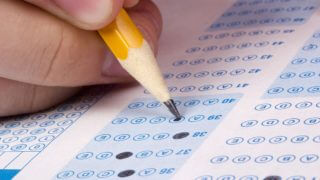
2021年(令和3年)宅建試験の試験日
上記のとおり、
宅建の試験日:令和3年10月17日(日)13時~15時(2時間)
となります。
ただし、試験地ごとに、受験申込者数が10月の試験会場の受験可能人員を上回った場合には、10月と12月に分けて試験を実施することになります。
12月試験となった場合、試験日は
令和3年12月19日(日)13時~15時(2時間)
となります。
※10月と12月のどちらの試験日での受験になるかは試験機関によって指定されます。
2021年(令和3年)宅建試験スケジュール
官報公告
2021年(令和3年)6月4日(金)
毎年、6月第1週の金曜日に、宅建業法に基づいて「実施公告」が官報に掲載されます。
なお、当公告は「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」のWebサイトにも掲載されます。
試験案内の配布
配布期間は、2021年(令和3)年7月1日(木)から7月30日(金)までとなります。
郵送申込みの場合は「試験案内」の入手が必要です(冊子版の「試験案内」には、受験申込書用紙が付属しているため)。
「試験案内」の配布場所は、試験実施機関の「一般財団法人 不動産適性取引推進機構」の試験案内配布場所のページをご覧ください。
インターネット申込みの場合は、「一般財団法人 不動産適性取引推進機構」のホームページに試験案内の内容を2021年(令和3年)7月1日(木)から掲載しますので、そちらを参考にしてください(冊子版の「試験案内」を入手する必要はありません)。
試験の申し込み
インターネット申し込みの期間
2021年(令和3年)7月1日(木)9時30分から7月18日(日)21時59分まで
※上記のとおり、インターネットの申し込み期限は郵送の申込期限(7/31)より2週間も早くなっています。忘れないように早めの申し込みをしてください。
郵送申し込みの期間
2021年(令和3年)7月1日(木)から7月30日(金)(消印有効)まで
※簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けされます。それ以外のものは受付けされないので注意してください。
試験日の通知
10月試験の指定を受けた方へは、試験会場通知(10月試験会場の案内図等を記載したはがき)が8月25日までに発送されます。
また、12月試験の指定を受けた方へは、12月試験の通知(12月試験の指定を受けた旨を記載したはがき)が8月25日までに発送されます。
受験票の発送
10月試験を受験される方へは令和3年9月28日(火)の発送です。
また、12月試験の指定を受けた方は令和3年11月30日(火)となります。
宅建の試験日(10月試験)
2021年(令和3年)10月17日(日) 13:00~15:00(2時間)
集合時間:12:30
※登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。
※ 当日は、受験に際しての注意事項の説明がありますので、12時30分までに自席に着席してください。
※ 試験時間中の途中退出はできません。 途中退出した場合は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。
合格発表(10月試験)
2021年(令和3年)12月1日(水)
宅建の試験日(12月試験)
2021年(令和3年)12月19日(日) 13:00~15:00(2時間)
集合時間:12:30
※登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。
※ 当日は、受験に際しての注意事項の説明がありますので、12時30分までに自席に着席してください。
※ 試験時間中の途中退出はできません。 途中退出した場合は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。
合格発表(12月試験)
2022年(令和4年)2月9日(水)
宅建試験制度の概要
ここでは、宅建試験制度の概要について見ていきましょう。
- 受験資格:年齢や性別、学歴による制約は一切なし
- 受験日:毎年1回、10月の第3日曜日の午後1時~午後3時
- 受験料:7,000円(消費税及び地方消費税は非課税)
- 試験会場:現在お住まいの試験地(都道府県)
- 試験科目:権利関係・宅地建物取引業法・法令上の制限・税その他
- 試験の方法:50問・四肢択一式による筆記試験
- 配点:権利関係14点・法令上の制限8点・宅建業法20点・税2点・その他6点
- 試験時間:13時から15時までの2時間(12時30分から注意事項の説明)
- 合格基準:目標点は36点~38点(相対評価なので合格点が年度で異なる)
年齢や学歴による制限はありませんので、宅建試験は誰でも受験できますよ。
宅建試験の一部免除とは?
宅建試験では、一部免除(5点免除)と呼ばれる制度が用意されています。
国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を修了し、試験に合格して3年以内であれば次の宅建試験が免除されるのが特徴です。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
50問中の5点が免除されますので、他の受験者と比べて試験に合格しやすくなります。
ただし、登録講習は宅地建物取引業に従事している方のみしか受講できません。
なお、一部免除(5点免除)の詳細については、下記記事を参考にしてください。
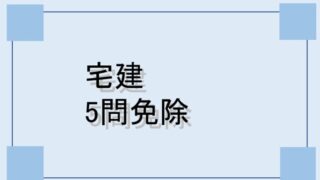
宅建試験の受験手続きにおける留意事項など
宅建試験の受験手続きの流れ(概要)は、以下のとおりです。
- 原則として、毎年6月の第1金曜日に、実施広告が官報および一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページで発表される。
- 毎年7月から一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページで、試験案内が掲載される
- 受験申込の受付が開始される(インターネットは毎年7月1日から15日まで、郵送は毎年7月1日から7月31日まで)
- 毎年8月頃に試験会場通知が送付される
- 毎年9月頃に受験票が送付される
- 宅建試験は原則的に毎年10月の第3日曜日に実施
- 毎年12月の第1水曜日または11月の最終水曜日に合格者が発表される
- 合格証書が送付される
宅建試験当日の注意事項
宅建試験を受けるに当たり、当日にはいくつかの注意事項がありますので、事前にきちんとチェックしておきましょう。
- 試験会場の場所や交通手段と所要時間を確認しておく(試験1時間前には会場に到着する)
- 「受験票」「筆記用具」「ハンカチ」「腕時計」「テキスト」などの持ち物をチェックする
- 午前中は丸暗記と苦手問題の復習を行う(宅建業法や法令上の制限を中心に)
宅建試験の解き方に関しては、難しい問題を飛ばして簡単な問題から解いていくのがポイントですね。
50問の中で30問程度は過去に出題されている簡単な内容ですので、「難しい問題に時間をかけすぎて全部を解けなかった・・・」という事態は防いでください。
※宅建試験の当日の持ち物については、下記の記事も参考にしてください。
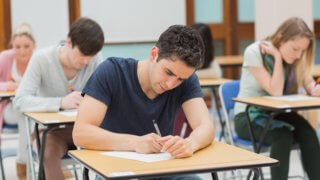
宅建試験の難易度は?勉強時間はどのくらい?
宅建試験の難易度がどのくらいなのか、勉強を始める前に気になっている方は多いと思います。
毎年の合格率は15%~17%程度ですので、司法書士など他の国家資格と比べてみるとそこまで難しいわけではありません。
国家資格の中でも合格できる可能性がかなり高いのですが、宅建試験の対策は独学ではなく通信教育で行うべきです。
なぜ通信教育で宅建の勉強をすべきなのか、考えられる理由を見ていきましょう。
- 自分のペースに合わせて学習を継続できる
- プロの講師に教わることで勉強時間を削減できる
- 自分で教材選びをする必要がない
- 法改正にも適切に対応してもらえる
何も知識がない状態だと200時間~300時間程度の勉強時間が必要ですので、通信教育で効率良く学習するのが効果的です。
なお、宅建試験の難易度や必要な勉強時間については、下記記事を参考にしてください。
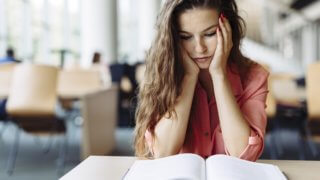

近年の宅建試験の受験者数や合格者数の推移
宅建試験の受験者数や合格者数がどう推移しているのか、以下では近年のデータをまとめてみました。
<年度 受験者数 合格者数 合格率>
平成25年 186,304人 28,470人 15.3%
平成26年 192,029人 33,670人 17.5%
平成27年 194,926人 30,028人 15.4%
平成28年 198,463人 30,589人 15.4%
平成29年 209,354人 32,644人 15.6%
平成30年 213,993人 33,360人 15.6%
令和元年 220,797人 37,481人 17.0%
上記でも説明しましたが、宅建試験の合格率は15%~17%程度ですので、知識ゼロの状態から学習を始めても受かります。
宅建試験の結果を分析してみた
宅建試験の結果を分析してみて、受験者数が毎年増加していることがおわかり頂けるのではないでしょうか。
それは私たちの生活と密接に関わる仕事で、需要がなくならないからです。
合格者数も徐々に増えていますが、「仕事がなくて就職や転職ができない・・・」なんてことはありません。
宅建試験の合格者の属性に関しては、「不動産業界に勤めている人」「初学者の女性」「10代から40代まで」と様々です。
「知識ゼロだから・・・」「もう40代だから・・・」と諦めている人はいますが、受験資格のない試験ですので積極的に宅地建物取引士(宅建士)を目指してみてください。
宅建試験とは?
宅建試験(宅地建物取引士資格試験)とは、宅地建物取引士(宅建士)になるための資格試験です。
不動産会社や金融機関で宅地建物取引士(宅建士)の仕事を行うには、宅建試験に合格して都道府県知事に対して登録手続きを行わないといけません。
宅地建物取引業を営む者は、日本の法律の宅建業法(宅地建物取引業法)に基づいて国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があると決められていますね。
宅建試験は日本の国家資格の一つで、宅建業法第16条の2の規定に基づいて各都道府県知事の委任のもとに実施されているのが特徴です。
宅建士とは?
宅地建物取引士(宅建士)は、毎年20万人が受験する人気の国家資格です。
試験に合格して都道府県知事の資格登録を受け、更に宅地建物取引士証の交付を受けた者が宅地建物取引士(宅建士)と呼ばれます。
以下では、宅地建物取引士(宅建士)が具体的にどのような業務と携わっているのかまとめてみました。
- 土地や建物の売買
- 賃貸物件のあっせん
- お客様が知るべき重要事項の説明
不動産会社を訪れる多くのお客様は、不動産に関する知識や売買経験を持っていません。
何も知らずに不当な契約を結ぶと思わぬ損害を被るため、在籍する宅地建物取引士(宅建士)がお客様に重要事項の説明をしています。
宅建士の登録について
宅建試験に合格しても、すぐに宅地建物取引士(宅建士)として仕事ができるわけではありません。
宅地建物取引士(宅建士)として業務を従事する方は、都道府県の登録を受けるのが必須要件です。
宅地建物取引士資格登録が受けられる人は、次の3つに分類できます。
- 宅地建物取引業の実務経験が2年間以上
- 国土交通大臣の登録を受けた宅地や建物に関する実務講習を修了
- 地方公共団体や設立された法人において、宅地や建物の取得または処分の業務に従事した期間が通算して2年以上
何をもって実務経験があると判断されるのかは、「申請時から過去10年以内」「全く別の仕事に就いていてはダメ」など細かい規定があります。
実務経験が2年未満でも実務講習(登録実務講習)を修了すれば宅建士として登録できますので、詳細は一般財団法人不動産適正取引推進機構の公式サイトをチェックしておきましょう。
参考:http://www.retio.or.jp/exam/entry_flow.html
※実務講習(登録実務講習)については、下記の記事も参考にしてください。

まとめ
宅建試験日や試験スケジュール、試験制度の概要についておわかり頂けましたか?
試験の合格基準や内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を持っているかどうかを判定することに基準が置かれています。
「難しそう」「難易度が高そう」とイメージしている方は多いものの、初学者で短期間で合格している方はたくさんいますので、宅建試験の学習をスタートしてみてください。
■
その他、宅建試験関連については、下記の記事も参考にしてください。
<試験概要>
<試験対策(総合)>
- 独学勉強法【人気】
- 独学のメリットとデメリット
- 独学向けテキストランキング【おすすめ】
- 難易度
- 必要な勉強時間、勉強する順番【おすすめ】
- 過去問の使い方【人気】
- 模試の活用方法
- 5点免除
<試験対策(科目別)>