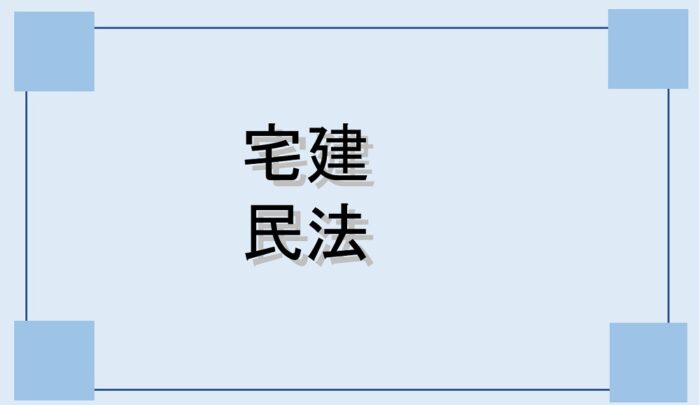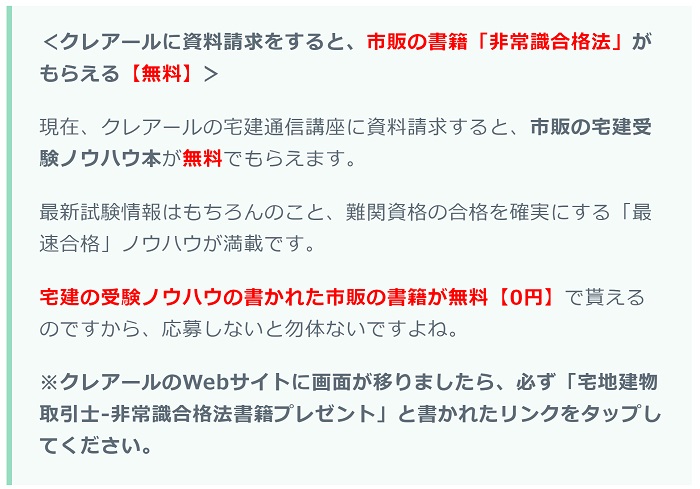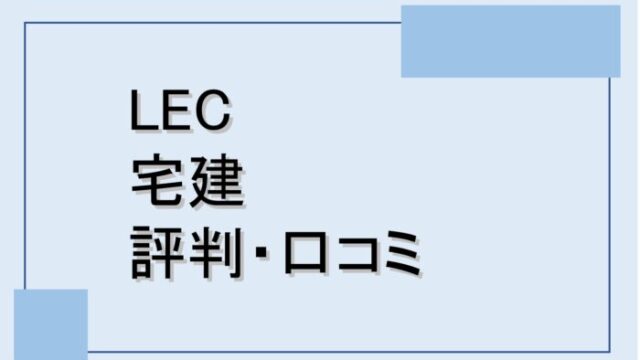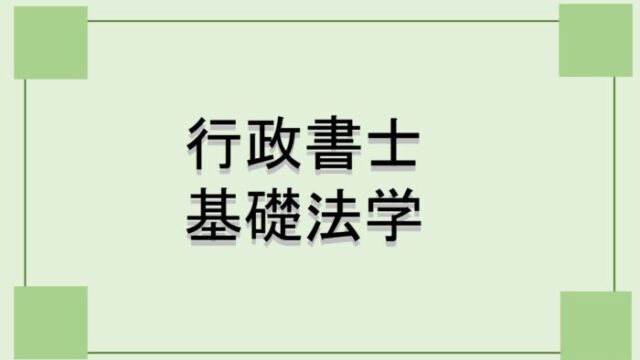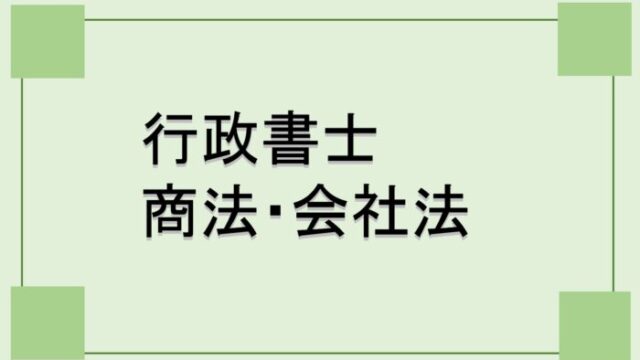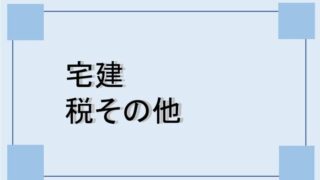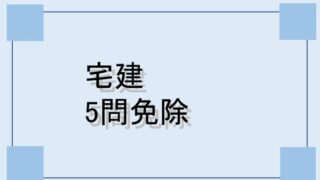こんにちは、トシゾーです。
宅建試験においては4つの分野から問題が出されますが、一番難しい(難易度が高い)と言われているのが権利関係(民法)です。
権利関係は、宅建試験においては14問出題され、そのうち10問と大半が民法の問題となっています(※ちなみに、残りは借地借家法・区分所有法・不動産登記法から4問)。
このように、難易度の高い権利関係の中でも大多数を占める民法の攻略は、「宅建試験の合否を分ける項目」といっても過言ではありません。
多くの方が苦手と思っている民法の問題を攻略すれば、おのずと合格が近づくのは言うまでもないでしょう。
この記事では、そんな民法の問題を攻略するための試験対策や勉強方法、攻略のコツについて説明したいと思います。
なお、現在クレアールに資料請求を行うと、市販の宅建攻略本を、無料プレゼントしています。
そちらも、ぜひチェックしてみてください。
=>クレアール 宅建試験攻略本(市販のノウハウ書籍)プレゼント付き資料請求はこちら
.
※画面遷移したら、下の方へスクロールして「宅地建物取引士-非常識合格法書籍プレゼント」と書かれたリンクをタップしてください。
.
目次
民法の概要
民法では、私人間の関係やトラブルの解決を図る
民法とは、私人と私人の関係やトラブルの解決に関して規定された法律です。
そもそも、法律は大きく「公法」と「私法」の2つに分けられます。
そのうち「私法」とは、民法のように「私人と私人の関係に着目した法律」のことです。
一方の「公法」とは、憲法や行政法のように「国家権力と私人(国民)の関係に着目した法律」のこと。
「私人間のトラブル・争い」については、「私法」に分類される民法・商法・会社法などで解決することになるのです。
宅建試験における民法の位置づけ(出題数)
民法の概要はこれぐらいにして、宅建試験における民法について見ていきましょう。
民法で出される問題数は?
まず、宅建試験の分野別問題数を確認します。
- 権利関係 14問
- 法令上の制限 8問
- 宅建業法 20問
- 税その他 8問
以上のように、宅建試験全50問中、権利関係(民法等)は全部で14問出題されます。
そのうち、民法が10問、残りが借地借家法(2問)、区分所有法(1問)、不動産登記法(1問)となっていますので、民法の問題数の多さは飛びぬけています。
さらに、借地借家法と区分所有法はどちらも民法に対する特別法でもあります。
つまり、借地借家法と区分所有法の学習においても民法の知識は必要不可欠なのです。
宅建試験における民法の重要性を、改めて感じた方も多いのではないでしょうか。
民法(権利関係)の得点目標
上記のとおり、宅建試験の問題数は全部で50問なのですが、権利関係から14問、うち民法からは10問が出題されます。
9割から満点を目指す宅建業法と違い、難易度が高い権利関係は14問中8問程度(60%程度)を目標としましょう。
詳しくは後述しますが、1,000以上の条文のある膨大な民法のうち、出題されるのは条文として100程度です。
しっかり出題頻度の高い部分を把握したうえで、本試験では6割以上取れればOKと考え、効率的な学習をすることが大切です。
宅建試験においては、民法を押さえれば有利になる!
宅建試験において、もっとも出題数の多い宅建業法は対策が容易であり、実際のところ、合格者の多くは9割以上得点しています。つまり差が付きにくい科目といえます。
一方、宅建業法の次に問題数が多い民法(権利関係等)は難解なため、きちんと理解していないと得点が伸びません。つまり、民法を押さえることができれば、俄然有利になるのです。
宅建業法などの他の科目は、まともに勉強すれば大体合計で30点近い得点が取れます。そして、民法を取りこぼさなかった人が最後に合格を手にするのだ、と心得ましょう。
民法出題形式
宅建の民法の問題では、条文そのものは、ほとんど出題されません。
出題のほとんどが事例問題であり、取引等の事例を説明しながら「民法の規定及び判例によれば、正しい(または間違っている)ものはどれか」という形式で出題されるケースがほとんどです。
そのため、条文を丸暗記しても意味がなく、条文や判例が「何を意味しているのか」という「法の考え方や背景」「法の精神」を正しく理解することが重要です(詳しくは次項で説明します)。
また、宅建試験はすべてマークシート形式ですが、4つの選択肢から「正しい物(間違っているもの)を選べ」という単純な形式ばかりではありません。
近年特に、個数問題(「正しい(or または間違っている)ものは、いくつあるのか?」と個数を問う問題)や、組み合わせ問題(「正しい(or 間違っている)ものの組み合わせを選べ」という問題)のように、すべての選択肢の正誤を理解できていないと正解できないような問題も増えています。
このことが、宅建試験の難化にも繋がっています。
宅建試験における民法の試験対策
宅建の民法は、条文と判例を知ることから始まる
前述のとおり、宅建の民法の問題は、
- 条文(規定)や判例と照らし合わせたうえで、正しい(正しくない)事例を選べ
というものです。
条文(規定)や判例そのものが出題される訳ではなく、「それら(条文や判例)を知識として知っておいたうえで」事例を選ぶ、という点がポイント。
とはいえ、1,000以上もある民法の条文を暗記しろ!と言っている訳ではありません。
民法の条文や判例について、「根本にある考え方」を理解する
必要なことは
民法の条文に込められた目的や、判決の理由などの「根本にある考え方」を理解する
となります。
これが、いわゆる「法の精神を知る」ことになります。条文の丸暗記をしても仕方ありません。しっかりと条文の目的や判例が下された理由を押さえることにより、民法の問題が解けるようになるでしょう。
実際に対策する条文は100程度
とはいえ、1,000以上もある条文の内容をすべて理解することも、現実的とは思えませんよね。
「自分には無理だ・・・」
と自信をなくしてしまう方もいるかも知れません。
しかし、1,000以上の条文の内容すべてを、きちんと把握する必要はないのです。
実は、宅建の本試験に出題される条文内容は、せいぜい100程度です。
つまり、
- 「頻出の問題である」「出題可能性がある」条文内容(100程度)だけを、しっかり仕上げる
- 残りの条文内容は「意味ぐらいは分かる状態にしておく」
という考え方が、あなたが取るべき戦略なのです。
実際、この戦略で私は短時間の勉強で一発合格することができした。
※【注意!】よく出題される条文(の内容)は100程度ですが、これらを様々に形を変え、事例問題として出題されるのが宅建の民法です。
決して「条文を100個、丸暗記すれば大丈夫」という意味ではありません。「100の条文内容について、正しく理解する」ことが必要です。
続いて、この勉強法について説明します。
宅建試験の民法の問題 勉強法
私が実践した、民法問題の短期合格勉強法は、次のとおりです。
宅建試験の民法 短期合格勉強法
①まずはテキストの民法の章を、ざっと一読する
②その際、論点ごとに問題集を解く(例:「委任契約」の項を読み終わったら、「委任契約」の問題を解いてみる)
③民法のテキスト・問題集を終えたら、続いて過去問10年分の民法の部分のみを解いてみる(主に、例年の過去問の問1~問10が民法からの出題です)
④過去問を解答して採点。誤った点はテキストの該当箇所を見て、しっかり復習をする
⑤正解した問題についてもテキストのその論点を確認して復習をする
いかがでしょうか。
以上の①~⑤の流れで、過去10年間に出題された論点が明確になりました。また、そのなかであなたの間違えた過去問は、特に徹底的に復習すべき論点といえます。
宅建試験の民法は、重要論点が繰り返し出題されます。つまり、あなたが明らかにした「過去10年間に出題された論点」だけを徹底的に理解することで、民法10問中、8~9問は必ず得点できるようになります。
とはいえ、人間の記憶は、繰り返し覚えないとすぐに忘れてしまいます。
時間に多少でも余裕があれば、民法のテキスト全体を、もう一週回すことで、重要ではない論点も、記憶に残るようにできればベターです。
しかし、忘れてはいけないのは、過去10年に出題された民法100問に出題された論点です。
ここだけを完璧にすれば、民法における合格ラインは必ず突破できると心得てください。
民法は図で理解する
民法は私人間の権利関係を規定した法律です。
そのため、「本人」「相手方」「代理人」「第三者」といった、様々な種類の人物が登場します。
これら登場人物の関係性は、図に書いて理解するのが重要です。
文字だけだと、正確な説明&理解は難しいため、あなたが使っているテキストにも必ず図で説明してあるはずです。
特に過去問を解く場合には、かならず図を書いて考えるようにしましょう。
手を使って図を書くことで理解が深まりますし、自信を持って正答できるようになります。
宅建試験の民法の問題 攻略のコツ【優先順位】
試験対策や勉強法のところでも書いたように
いかに、徹底的に理解する論点を絞るか
ということが、宅建試験の民法の攻略のコツです。
以下に、過去10年間に出題が多い/少ない論点の例を挙げてみました。
過去10年間における出題が多い論点(テーマ)
過去10年間における出題が多い論点(テーマ)としては、以下のようなものがあります。
抵当権、相続、代理・復代理、時効取得・消滅時効、担保責任、制限行為能力者などの関連
出題頻度の小さい論点(テーマ)
出題頻度の小さい論点(テーマ)としては、以下のようなものです。
先取特権、根抵当権、贈与契約、使用貸借契約、消費貸借契約、債権譲渡契約、不当利得、債権者代位権、地役権、占有権、質権、留置権
以上が、出題の多い/少ないテーマとなります。
ここで強調しておきたいのは
必ず民法の過去10年分の問題全問(100問)を自分で解いてみて、自分自身で「確かに、このテーマは頻出だ」と納得したうえで、テーマの絞り込みをして欲しい
ということです。
自分で過去10年分・100問を解いてみて、頻出テーマを「自分の体験として実感」することにより、心から自信を持って、テーマを絞った学習ができるようになります。
あまり精神論的なことは好まないのですが、
- 民法の過去問題10年分すべて解くことで、自分自身の自信につながる
- 「この論点は頻出だ」と自分自身で発見することで、心から自信を持って勉強する範囲を絞ることができる
という2点は、何気に学習効果に響いてくると感じています。
資格試験の合否って、結構な部分で、その受験生の気の持ち方による部分が大きいものです。
ぜひ、自分自身で頻出論点を見つけ出してください。
【参考】2020年の民法の大改正
宅建試験の出題は、その年の4月1日現在に施行されている法令・規定が対象です。
少し前に話題となった「民法大改正」とは、2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法のことです。
宅建試験では、法改正の対象箇所は出題の対象となりやすいため、改正点を中心に学習することは大切です。
「直近、改正された部分は?」ということを頭の片隅において、学習をして欲しいと思います。
まとめ
ここまで、宅建試験「権利関係・民法」の概要から試験対策、問題攻略のコツなど詳しく説明してきました。
宅建試験の出題分野のなかで、「もっとも範囲が広く、もっとも難易度が高い」といわれる民法ですが、
頻出部分・出題可能性のある部分を絞れば、恐れることはありません。あなたも是非、この今回の記事を参考にして、合格を目指して欲しいと思います。
忙しい方が資格取得を目指すなら、スマホ対応の宅建オンライン通信講座がおすすめ
これから宅建の合格を目指す方のなかには、社会人や主婦の方など、なかなか勉強時間を捻出できない多忙な方が多いと思います。
そのような方は、時間や場所を選ばずに、スキマ時間にスマホで学習できるオンライン動画う対応の宅建通信講座を検討してみてはいかがでしょうか。
スクール各社から様々な特徴を持つオンライン通信講座が発売されていますので、よろしければ以下の記事をチェックしてみてください。