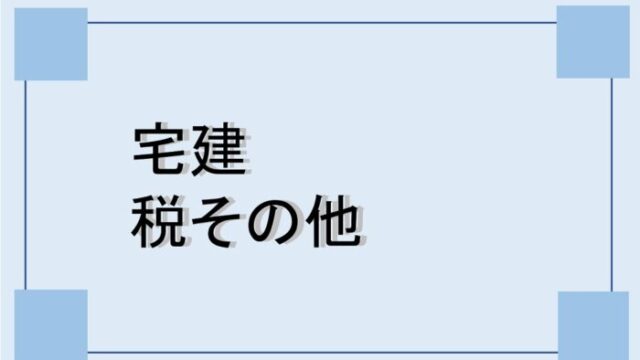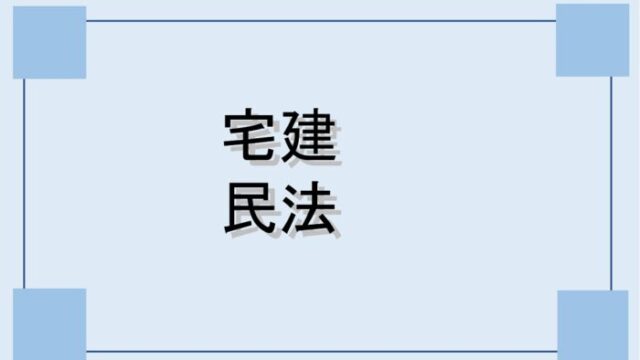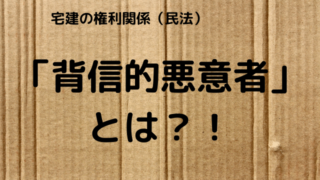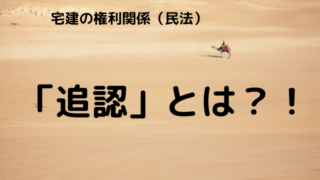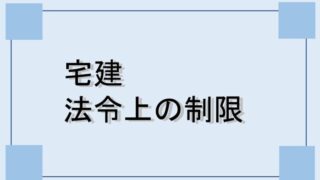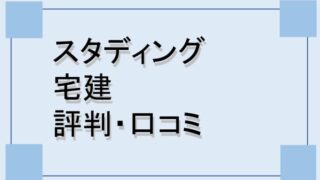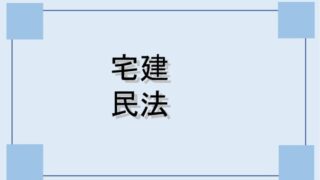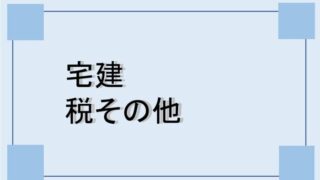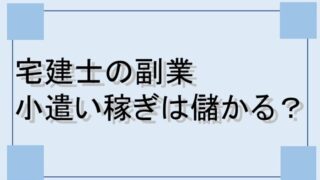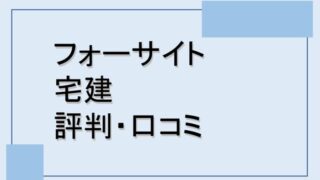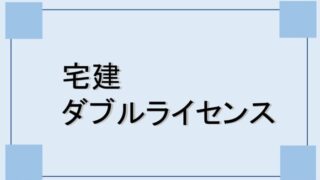こんにちは、トシゾーです。
今回は、宅建の模試について、活用方法や注意事項をご説明します。
人によっては、
「模試なんて受けるだけムダだ!」
と言われる方もいますが、私は、そうは思いません。
私は、宅建の模試をうまく利用することにより、合格する力を大きく伸ばせる、と考えています。
というわけで、
- 宅建の模試を、どのように活用すれば、自分の力を伸ばせるのか?
- 公開模試(会場受験・自宅受験)と市販模試のどちらがおすすめ?
- 2022年の公開模試と市販模試の情報のまとめ
などについて、この記事で説明していきます。
模試の活用を考えている方も、模試の活用に否定的な方も、参考にして頂けるとうれしいです。
宅建の模試を受験するメリットとデメリットはこれだ!
宅建の資格取得を目指すに当たり、模試(模擬試験)や答練(答案練習会)は受験しておくべきです。
宅建試験の攻略において、まずは過去問を解くことが第一ですが、それだけでは本番の試験に実力を出せないこともあります。
※過去問を使った勉強法のポイントについては、下記記事を参考にしてください。
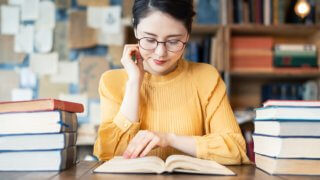
実践力を養って合格に近づけるためには、模試が大いに役立ちます。
まずは宅建の模試を受験するメリットについて見ていきましょう。
- 公開模試(会場受験)では、本試験と同じような環境で受験する形になるため、本番の直前に予行演習ができる
- 問題の時間配分や解く順番など、日々の勉強では難しい部分を掴むことができる
- 「知識を上手く当てはめられない」「覚えたはずの条文が出てこない」など、普段の学習では見えてこない課題を把握できる
- 自分が得点できなかった部分の苦手科目を分析し、克服して確実に点数を伸ばすことができる
- その年の本試験に出題される可能性の高い問題をチェックして集中的に補強できる
- 予備校で実施されている公開模試の中には、コンピュータ採点で弱点を細かく洗い出して復習すべきポイントを把握できるものもある
宅建の本試験は2時間で50問が出題され、試験の範囲や科目はかなりのボリュームがあります。
いきなり本試験に挑むよりも、模試で解き方のコツを把握していれば得点を取れる可能性が高いのです。
それに加えて自分の学習の進み具合を確認したり苦手分野を補強したりといった対策もできますので、宅建の模試のメリットが大きいとおわかり頂けるのではないでしょうか。
しかし、宅建の模試を受けるに当たり、金銭的な負担が加わるというデメリットがあります。
予備校によって違いがありますが、直前期に実施される宅建の公開模試は1回当たり3,000円~5,000円程度です。
※6~7月に実施される早期の公開模試には0~1,000円台のものもあります(LEC)。
とは言え、お金がかかる以外に宅建の模試のデメリットは特にありません。
「模試を受けて失敗だった・・・」と感じることはほぼありませんので、本番前の予行演習として受験してみてください。
宅建の模試は会場受験と市販模試のどっちがおすすめ?
宅建の模試は、次の2種類に大きくわけることができます。
- 予備校で実施される公開模試(会場受験)
- 自宅で受験する公開模試(自宅受験)
- テキストを購入して自宅で問題を解く市販模試
いずれの方法でも、宅建試験の本番に備えた対策ができる点では一緒です。
本番の試験さながらの環境で受験したいのであれば「会場受験」、仕事が忙しくて会場受験の時間を確保できない人は市販模試がおすすめです。
※個人的には、公開模試(自宅受験)はおすすめしておりません。自宅で解くなら、市販模試の方が圧倒的に安いからです(詳しくは後述)。
宅建の模試で公開模試(会場受験)がおすすめの理由
大手予備校の直前期の公開模試(会場受験)は1回当たり3,000円~5,000円で、1冊1,500円~2,000円程度で購入できる宅建の市販模試よりもコストがかさみます。
しかし、宅建の模試は市販模試よりも会場受験の方がおすすめで、その理由をいくつか見ていきましょう。
- 他の受験生と同じように会場に集まって試験を受ける形になるので、慣れておけば本番の緊張やプレッシャーがほぐれる
- 後日の分析結果により、出題された問題ごとの正解率が分かるため、「正解率の低い問題は捨てる」といった対策を立てられる
- 成績表には自分の順位や偏差値が出るため、ライバルとどの程度の差がついているのか把握できる
宅建の模試のメリットを活かしたいのであれば、市販模試よりも会場受験ですね。
「TAC」「LEC」「大原」「日建学院」など、確かな実績を持つ予備校で実施されている宅建の模試を選んでいれば間違いはありません。
なお、会場受験の際は、できるだけ大規模な教室で実施する模試を選んでください。
というのも、宅建の本試験は、数百人が収容できる教室で行われることがほとんどです。
そのため、少人数の模試では、本番の練習やシュミレーションとしては、今ひとつです。
各社の公開模試の一覧
| 実施機関 | 名称 | 日程 | 価格 |
| Kenビジネススクール、通学の日建学院、住宅新報、資格の大原(共催) | ジ・オープンMOGI ※2022年度開催は未発表 |
9月実施予定 | 5,500円(2021年度の場合) |
| LEC、総合資格学院(共催) | 宅建士模試 | 9月実施予定 | 6月販売開始 |
| LEC | 宅建実力診断模試 | 2022/6月中(会場による) | 1,650円 |
| LEC | 0円模試 | 2022/7月中(会場による) | 0円 |
| LEC | 全日本宅建公開模試 基礎編 | 8月実施予定 | 後日販売開始予定 |
| LEC | 全日本宅建公開模試 実戦編 | 9月実施予定 | 後日販売開始予定 |
| LEC | ファイナル模試 | 10月実施予定 | 後日販売開始予定 |
| 日建学院 | 全国統一公開模擬試験 | 10/2 | 5,500円 |
| TAC | 全国公開模試 | 9~10月実施予定 | 5,500円(2021年度の場合) |
各社の市販模試 一覧
各社の市販模試(2022年版)は、いずれも2022年6月頃の販売予定です。
| 販売元 | 名称 | 価格 | 備考 |
| TAC出版 | 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 | 1,760円 | 2022/6/8発売、予想模試4回分+本試験2回分 |
| LEC(東京リーガルマインド) | 出る順宅建士 当たる! 直前予想模試 | 1,760円 | 2022/6/7発売、予想模試4回分+本試験2回分 |
| TAC出版 | みんなが欲しかった! 宅建士の直前予想問題集 | 未定 | 予想模試4回分 |
| 住宅新報出版 | パーフェクト宅建士 直前予想模試 | 未定 | 予想模試3回分 |
| インプレス | 合格しようぜ! 宅建士 直前予想模試 音声解説付き | 未定 | 予想問題3回分+試験直前ダウンロード問題1回分 |
宅建の市販模試は、図書館で利用しよう!
「なるべくお金をかけたくない」「予備校まで遠くて時間がかかる」という方は、宅建の市販模試がおすすめです。
「市販模試の質やレベルは低いのでは?」と不安に思っている方がいるかも知れません。
しかし、内容に関しては、会場模試と比べて見劣りするものではありません。
というのも、市販模試は、TACやLEC、日建学院といった、模試も実施している代表的な資格の学校が発行しているからです。
ただ、市販模試の最大のデメリットは、
会場模試のように、実際の本試験を受験しているような雰囲気を味わえない
ということです。
前述のとおり、会場模試は、本番試験をシュミレーションできる、ということが最大の特長です。
そのため、
本試験と同じような環境で受験する形になるため、本番の直前に予行演習ができる
問題の時間配分や解く順番など、日々の勉強では難しい部分を掴むことができる
以上のような大きなメリットがあるのです。
しかし、模試会場が近くにない場合などは、どうすることもできません。
その場合は、市販模試を図書館で時間を計りながら解答することがおすすめです。
図書館の静寂な雰囲気の中で模試に取り組めば、多少なりとも、実際の本試験のシュミレーションはできるはずです。
きちんと時間を計って本番のつもりで取り組むことにより、今まで気が付かなかった課題を発見できることでしょう。
宅建の模試の受験回数はどれぐらい?
「宅建の模試は何回くらい受ければ良いの?」と疑問に思っていませんか?
特に宅建の模試について、おすすめの受験回数があるわけではありません。
1回の模試で時間配分や解く順番のコツを把握できるとは限りませんので、「納得できなければ2回」「結果が出なかったから3回」と増やしてみてください。
複数回に渡って宅建の模試を受けるのであれば、いくつかの予備校の会場受験の模試を1回ずつ受ける方法がおすすめです。
会場受験と市販模試を併用し、本番の試験に備えて徹底的に対策するのも良いでしょう。
ただし、模試を受けた後は、必ず復習をしてください。
復習をしないのであれば、模試の効果は半減してしまいます。
また、模試の受験や復習の時間によって、通常の学習時間が削られるのであれば本末転倒です。
しっかりと、あなたの学習計画のなかに模試に必要な時間も組み込んで、効果的な受験をしてください。
宅建の模試が終わった後に必ず復習する
宅建の模試を受けて結果が出た後は、必ず復習をしましょう。
模試は高得点を取るのが目的ではなく、自分の弱点や苦手分野を知るために受験します。
苦手分野をそのまま放置していると本番の宅建試験で合格することはできませんので、模試の結果を見た後に「○○○の勉強にもっと力を入れた方が良いのか~」と復習すべきです。
具体的にどのような方法で宅建の模試の復習をすれば良いのか見ていきましょう。
- 自分が解いた問題冊子を見返して、判断に迷った問題と理解できなかった問題をピックアップする
- 解説冊子と問題冊子を照らし合わせて、どうすれば解けたのか把握する
- 後から思い出すことができるように、間違った問題と解説をノートに残しておく
仮に宅建の模試の結果が悪かったとしても、「やっぱり自分には無理なんだ・・・」と諦める必要はありません。
模試と同じ結果にならないように復習を中心に学習計画を立てていれば、本番の試験で合格できます。
宅建の模試を受けるメリットとデメリット!模試を受ける際のおすすめの方法は? <まとめ>
宅建の模試は金銭的な負担以外は、特に大きなデメリットはありません。
本番の試験の前に模試を受験すれば、「予行演習ができる」「問題の解き方がわかる」「苦手分野を克服できる」など様々なメリットがあります。
宅建の模試を受けた後の復習を重視していれば合格率を高めることができますので、是非一度試してみてください。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |