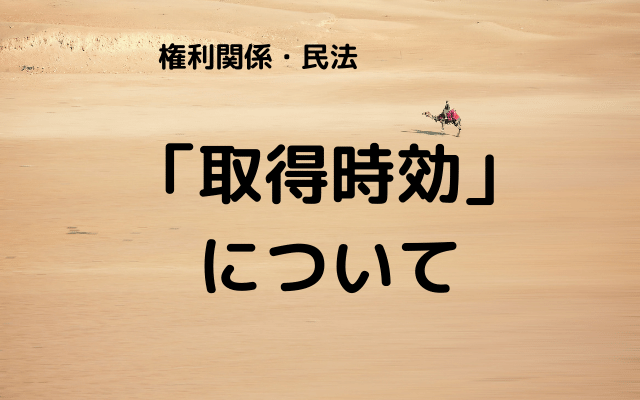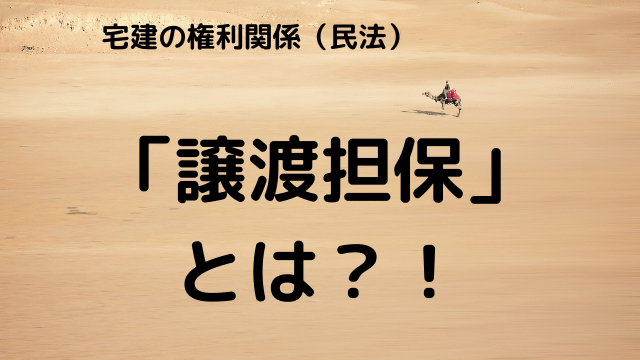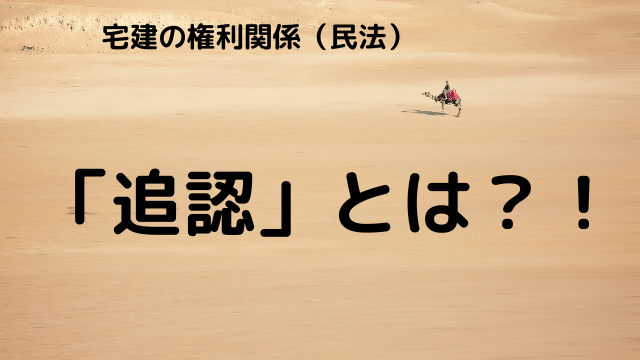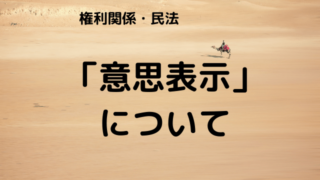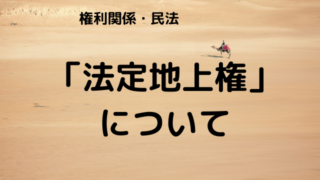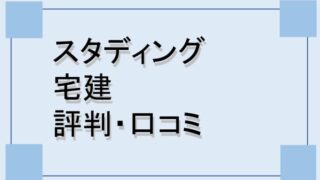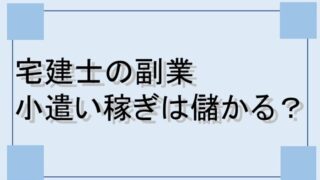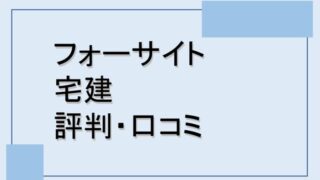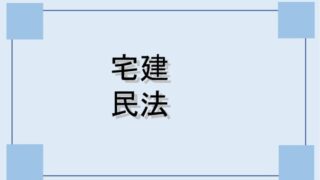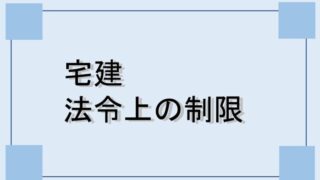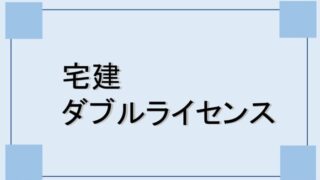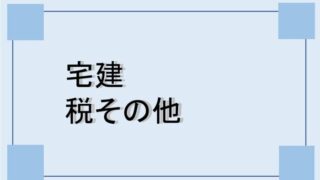取得時効とは?
取得時効とは、長い期間に渡って所有の意思を持って他人の物を平穏に占有した時に、所有権などの権利を取得できる定めです。
不動産における所有権の取得時効は平穏に公然と占有していた場合、自分に所有権があると思い込み(善意)、過失がなければ(無過失)10年後に自分の物になります。
善意かつ過失なしで占有する時は10年の短期取得時効、それ以外のケースでは20年の長期取得時効ですね。
民法第162条では、取得時効について下記のように規定しています。
- 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
参考:民法第162条(WIKIBOOKS) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC162%E6%9D%A1
いずれの場合でも、「所有の意思を持つ」「平穏かつ公然と」他人の物を所有する点では変わりありません。
取得時効の対象となる権利
取得時効の対象となる権利は主に次の4つです。
| 取得時効の対象となる権利 | |
|---|---|
| 所有権 | 特定の物を自由に使用や収益、処分できる権利 |
| 地上権 | 工作物を所有するために他人の土地を使用する権利 |
| 地役権 | 自分の土地の利用価値を増すために他人の土地を利用する権利 |
| 不動産賃借権 | 一般の賃借権は債権であるため取得時効の対象とはならないが、不動産賃借権については取得時効の対象となるという判例が出ている |
時効の認められる権利なのかどうかが取得時効の条件になります。
取得時効の要件
取得時効の要件は、「所有権」「地上権」「地役権」「不動産賃借権」なのかどうかだけではありません。
他にも取得時効として認められるには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
取得時効の要件1:所有の意思
取得時効の要件の一つは、所有の意思があるかどうかです。
所有の意思とは、「自分の物としたい」という内心の意思を保有している状態を指します。
例えば、マンションの部屋を賃貸して毎月家賃を支払っている人は、その部屋はマンションオーナーの物である旨を認識しているため、自分自身で所有する意思はありません。
逆に他人を脅して、他人の持ち物を強奪した人は自分の物にしようと考えていますので、内心の意思を持っていると判断できますよ。
つまり、賃借や使用貸借のような占有はこの意思が認められません。
取得時効の要件2:一定の期間
土地の所有権の取得時効が成立するには、決められた時効期間を満たしていることも必要です。
まず、時効期間の開始は、自分自身が所有する意思を持って、対象物の所有を開始した時期となります。
その「所有開始の時点」において、その対象物を自分の物だと思い込んでいた(善意の)場合は、10年間が時効期間となります。
また、自分の物ではない(他の誰かの物である)と事情を知っていた(悪意の)場合は、20年となります。
上記の項目でも解説しましたが、10年間の時効期間の経過による所有権の取得は短期取得時効、20年間の時効期間の経過による所有権の取得は長期取得時効と呼びます。
取得時効の要件3:公然と占有
最後の取得時効の要件は、公然と占有しているのかどうかです。
わかりやすく解説すると、暴力的に奪ったり隠匿したりしていない状態を指します。
上記の例で時計の強奪は所有の意思がありますが、平穏にかつ公然と他人の物を占有したとは言えません。
結果的に時計の所有権を取得できないので注意が必要です。
時効の援用
時効とは、時間が経過することで、権利が移動する制度になります。
取得時効における時効の援用とは、時効の効果の発生を確定させるための意思表示のことですね。
当事者が時効を援用しない限り、その効果は発生しないので利益を受け取ることができません。
民法第145条では、時効の援用について以下のように定められています。
「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
参考:民法第145条(WIKIBOOKS) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC145%E6%9D%A1
時効の援用の制度は、時効により利益を得る者の意思を尊重するために設けられました。
時効完成の効果
時効完成の効果は、起算日(時効期間を数え始める日)に遡って生じます。
例えば、他人の土地を20年間に渡って占有して時効を取得した場合、20年前からその所有者だったという判断です。
もし時効完成の効果を認めないと、20年の間ずっと他人の土地を占有し続けていた、という状態になり、「その間の土地代(地代)はどうなる?」「一括で支払ってもらうのか?」など、話が大変ややこしくなります。
お金を請求できる権利を行使せずに時効が成立したケースも同じで、起算日からその権利を有していなかったことになるわけです。
占有の承継とは?
取得時効との関係で、占有の承継は大きな問題の一つになります。
占有の承継とは、所有の意思を持って不動産の占有を始めた者が取得時効の完成前に他人に譲り渡した場合、時効が成立時期はいつなのか?ということです。
例えば、Aさんが所有する土地にBさんが占有の開始日に善意無過失で入り込み、8年目に自己の土地としてCさんに売却したとします。
Cさんは悪意で3年間に渡ってその土地を占有していましたが、CさんはAさんの土地を時効取得できるのかどうかという問題が占有の承継です。
上記のケースでは、土地の占有がBさんからCさんに引き継がれています。
民法では、「占有者の承継人は自己の占有だけを主張するか、または前の占有者の占有を併せて主張するか、を選択できる」「前の占有者の占有を併せて主張する際はその瑕疵をも承継する」と定められています。
結論として、Cさんは好きな方を選べます。Cさんの前に占有していたBさんは善意だったため、Bさんの占有も合わせて主張すれば、「善意で占有開始して11年」ということで、時効が成立(Cさんが時効の援用ができる)ことになるのです。
時効の完成猶予・更新とは?
時効の完成猶予とは、一定の完成猶予事由が生じた際に所定の期間、時効の完成が先延ばしにされる制度を指します。
時効の完成間近になっても債権回収の話し合いがまとまっていない場合など、債権者側が時間を稼ぎたい時に時効の完成を延期できる仕組みです。
一方で時効の更新は、時効のカウントダウンが一度リセットされます。
時効の更新が認められると、時効のカウントダウンが無くなってしまい、また一から時効のカウントダウンを始めなければなりません。
以下では、民法に規定されている時効の完成猶予・更新事由をまとめました。
完成猶予・更新事由 完成猶予 更新 裁判上の請求等 事由終了時まで完成猶予 確定判決・判決と同一の効力を有する権利の確定で更新 強制執行等 事由終了時まで完成猶予 事由終了により更新 仮差押え等 事由終了時から6ヵ月間の完成猶予 更新できない 協議を行う旨の書面による合意 合意から1年または合意で定めた協議期間の経過 更新できない 催告 催告時から6ヵ月間の完成猶予 更新できない 天災等の事変による裁判上の請求・強制執行不可 障害の消滅時から3ヵ月間の完成猶予 更新できない 参考:時効の完成猶予・更新について(東京中央総合法律事務所) https://www.tcs-law.com/saikenkaishu_kiso/jikou-yuuyo.html
権利の消滅を防ぐ役割を果たすのが時効の完成猶予と更新です。
時効の利益の放棄
時効の完成で利益を受ける者が利益を放棄することを「時効の利益の放棄」と言います。
民法第146条では、以下のように規定されています。
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない
参考:民法第146条(WIKIBOOKS) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC146%E6%9D%A1
時効の利益をあらかじめ放棄できると、お金を貸す人が、借金を申し込んだ人に対して、
「時効が来ても、時効を主張しないと約束してください。じゃないと、お金を貸さないよ!」
と、立場の弱い者に対し、最初から時効の利益を放棄させることを強要することができてしまうのです。
そのような強要を防ぐために、時効の完成前に利益を放棄できないと定められました。
ただし、時効の完成後に利益を放棄するのかどうかは個人の自由です。
まとめ
取得時効の要件や時効完成の効果、時効の完成猶予・更新についておわかり頂けましたか?
法律上では、「所有の意思がある」「平穏で公然と占有している」「他人の物を一定期間、継続して占有している」「時効の成立を主張する」などの要件を満たすと、取得時効が成立します。
宅建試験では権利の時効取得に関する問題が出題されていますので、正しい法律や考え方をマスターしておきましょう。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |